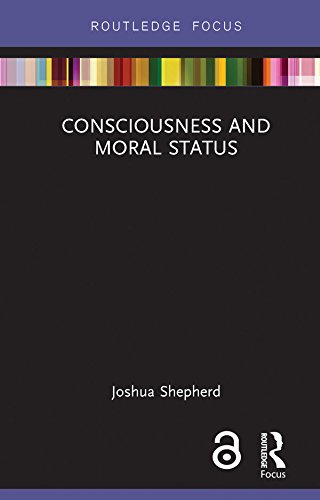- De Neys W. (2021), On Dual- and Single-Process Models of Thinking. Perspectives on Psychological Science.
序
明らかな事実として、思考には簡単なものと難しいものがある。このことを説明するのに、人間の心には二種類の質的に異なる心理過程(直観・熟慮)があるとするのが「二重過程モデル」だ。このモデルは極めて人気が高いが、批判もある。批判者は、二つの思考過程の違いは単なる程度の違いだとする「単一過程モデル」を支持する。2つのモデルの争いは長年続けられてきた。
この状況に対し、本論文は2つのことを主張する。第一に、目下のところ、論争を決着させるような経験的データや理論的原理は存在しない。第二に、仮にこの論争が決着したとしても、それは思考の基盤となる心理処理メカニズムの理解に寄与しない。結論として、経験科学者がこの論争をこれ以上続けることは不毛である。
事前の注意
- 【二重と多重】
本論文では「二重過程」という語を使うが、議論は2つ以上の思考過程をおくモデル(多重過程モデル)全てに当てはまる。
- 【プロセスとシステム】
二重「プロセス(過程)」と二重「システム」という語を、モデルのスコープの広さ(特殊/一般)に応じて使い分ける人がいる。しかし本論文の議論はどちらのスコープのモデルにも当てはまるので、ここでは両表現を互換的に用いる。
なお、「二重システム」と呼ばれる見解の中には、直観/熟慮のもつ様々な特徴(早い・楽..../遅い・努力を要する....)は全て共起すると考えるものがある。これは特に「完全連携型」(parfect-alignment)二重過程モデルと呼ぶことにする。
- 【モデル、理論、フレームワーク、説(view)】
全て互換的に用いる
- 【一般的モデル】
二重過程モデルの具体的な形は主唱者によってかなり異なる。しかし論争の際には、二重過程モデルの支持者も批判者も、なんらかの一般的モデルを想定して話をする傾向があり、これは藁人形論法になっている可能性がある。本論文における「二重過程モデル」は、そうした一般的モデルを指すのではなく、直観的思考と熟慮的思考に質的違いを認めるあらゆるモデルを指す。話がより細かくなる場合は、誰のモデルを念頭にしているか明示する。
- 【検討範囲】
この論文では、思考に関する二重過程モデルのみを扱う。記憶や学習などは直接には取り扱わない。
第1部 両モデルに関する議論
1. 特徴の連携
二重過程理論は、各過程が持つとされる様々な特徴を列挙した表と共に導入されがちである。実際、そこで提示される特徴の多くが相関しているというのは確かだ。しかしより極端に、これらの特徴は必ず共起すると主張される場合がある。そしてこうした特徴間の完全な連携が、2つの過程に質的な違いがあることの証拠として用いられる(完全連携型二重過程モデル)。
しかし、完全連携型二重過程モデルには多くの点で問題がある。第一に、特徴の連携は、両過程の質的相違を必ずしも意味しない。逆に、特徴が連携していないからといって、両過程が質的に同じだとも限らない。二重過程モデルは2つの過程が質的に違うと言えればいいのだから、何らかの一次元での質的違いがあればそれで十分である(Evans & Stanovich, 2013; Pennycook et al., 2018)。つまり、連携の問題は過程数の問題とは独立である。
第二に、特徴間の完全連携は多くの経験的証拠に反している。例えば孵化効果(Wallas 1926)は楽だが時間がかかる思考過程であり、努力と速さが必ずしも相関しないことを示す。また、合理化(Evans & Wason 1976)が示すように、熟慮と正確性は必ずしも相関しない。こうした非連携はこれまでも数多く指摘されてきた。
ただし特徴の非連携は、二重過程モデルそのものを否定する材料にはならない。二重過程モデルの批判者はしばしばそのように論じてきたが(Keren & Schul 2009; Melnikoff & Bargh 2018; Osman 2004, 2018)、そこでは極端な完全連携型モデルと二重過程モデルそのものが同一視されてしまっている。上述したように、二重過程モデルに特徴の連携は必要ないのだから、連携のありかたを経験的に観察しても論争に決着はつかない。
2. 定義的特徴
近年の二重過程理論家は完全連携を明確に否定し、二重過程理論はあくまで一つの特徴にかんする質的相違しか主張していないと強調している(Evans & Stanovich 2013; Stanovich & Toplak 2012)。この特徴は「定義的特徴」と呼ばれる。では、定義的特徴とは具体的には何なのか。近年の議論では、特に「ワーキングメモリの関与」、「認知的分離・心的シミュレーション」、「自律性」の3つが候補としてあげられてきた。ここで次に問題となるのは、こうした定義的特徴はその本性上二分法的なものではなく、連続的なものだという点だ。そこで、直観的過程と熟慮的過程を分かつ閾値をどこかに設定する必要がある。しかし現在提起されている定義的特徴はあまりにも曖昧であり、閾値設定は非常に困難なものになっている。具体的に見ていこう。
a. ワーキングメモリ
記念碑的論文であるEvans & Stanovich (2013) は、熟慮過程の第一の定義的特徴をワーキングメモリへの負荷だとした。この提案の問題は、ワーキングメモリの本性や特徴については非常に様々な見解があるため、さらなる明確化が必要だということだ。また近年、ワーキングメモリ、特にそれを支える制御的注意は、無意識的にも働くことが明らかになってきている(Desender et al. 2013; Jiang et al. 2015, 2018; Linzarini et al. 2017)。つまり、ワーキングメモリや制御的注意の関与は連続的なものだ。この時もちろん、熟慮的思考は直観的思考より広範な注意制御を必要とするという複雑性の違いはある。しかし、両過程を分ける閾値をどう決定すればよいのか。
ここで、認知的制約をかけた状態でのパフォーマンスの変化に訴えることで、推論過程が熟慮的か否かを操作的に定義することはできる。しかしこのことは、熟慮過程と直観過程が質的に異なることを意味しない。なぜなら、両過程の違いは量的だという単一過程モデルでも、熟慮過程は直観過程より多くの注意制御(ワーキングメモリ)資源を必要とすると仮定できるからだ(Keren & Schul 2009)。認知的制約パラダイムでは、過程の差異が量的か質的かについては何も結論できない。
b. 認知的分離・心的シミュレーション
Evans & Stanovich (2013) は、熟慮過程の第二の定義的特徴を認知的分離(現実の表象と想定上の表象の切り離し)および心的シミュレーションだとした。確かに一般的な特徴づけとしては、熟慮的思考に仮説的思考が含まれることは多いだろう。しかしこの特徴を、熟慮的・直観的過程を質的に分ける基準とするには、認知的分離・心的シミュレーションをより特定化する必要がある。Stanovich (2011) はその特徴づけと記述に力を費やしているが、現在のところ心的シミュレーションの発生を操作的に測定する方法は明確にされておらず、認知的負荷が大きいなどの相関的特徴が測定されているにすぎない。
ところで、Evans & Stanovich (2013) はワーキングメモリと心的シミュレーションの2つを定義的特徴としている。つまり、この場合2つは必ず共起しなければならない。しかし、心的シミュレーションを用いるがワーキングメモリが関与しない過程があるかもしれない。例えば後悔はそうかもしれない(Osman 2013)。
c. 自律性
二重過程理論支持者のなかには、直観過程の定義的特徴として自律性を挙げるものがいる(Pennycook 2017; Thompson 2013)。この場合の自律的過程とは、トリガー刺激に対して実行が強制される過程である。ここでも、一般的な記述としてならこの提案は理にかなっているが、より正確で検証・操作可能な形に落としこもうとするとすぐに問題が生じる。
ここで重要なのは、ある刺激Xが反応Yを強制的にもたらすかどうかは、現在の課題や目標の文脈に依存していることだ。例えば、「| + | = ?」という刺激に対し、大抵の大人は「2」と考えざるを得ない。しかし例えば、「与えられた複数の縦棒を横にして連結した場合の長さを求める課題」に習熟していれば、「| + | = ?」には「____」が浮かぶだろう。したがって、自律性の存在を主張するためには、目標文脈を確定するための独立したテストが必要になる。しかしこのような特定化はこれまで全くなされていない。
なおEvans (2017, 2019) は、自律性は直観的思考の定義的特徴としては広すぎると見解を改め(多くの低次の知覚過程までもが直観的思考になってしまうため)、次の追加基準を提案している。典型的な直観的思考において、主体はその出力を意識する(例えば簡単な計算の場合、その答えが正しいと感じる(Thompson et al. 2011))。つまり、直観的思考過程はその動作においてはワーキングメモリを必要としないが、アウトプットをワーキングメモリにポストするという点で、知覚過程などとは異なる。この提案は様々なタイプの直観過程を区別できる点で興味深いが、過程の数をめぐる目下の論争には役に立たない。自律性とワーキングメモリという2つの曖昧な概念をどう測定するのかという問題が引き続き残っているからだ。
小括
以上のように、これまで提案されてきた定義的特徴は十分に定義されていないため、質的に異なる処理をもたらす正確な閾値を設定することができていないという一般的な問題がある。
3. 基準S
Sloman (1996) は、人が矛盾した信念を同時に持ちうることが二重過程モデルを支持すると主張した(「基準S」)。というのも、質的に等しい推論システムは、一度に一つの応答しか出すことができないと考えたからだ。この議論は繰り返し批判されてきたが(Gigerenzer & Regier 1996; Keren & Schul 2009; Osman 2004)、現在でも二重過程モデルの正当化に用いられ続けている(Hoerl & McCormack 2019)。しかしこの議論の問題点は、「相矛盾する同時的反応は質的に異なる推論過程から生じているはずだ」という仮定を支持する経験的証拠がない点だ(Keren & Schul, 2009)。
4. 倹約
ここまでで、単一過程モデルと二重過程モデルの論争を経験的に決着することが難しいと述べてきた。そこで一部の研究者は、より理論的考察に訴えて決着をつけようとしている。例えば、理論的倹約の観点から単一過程モデルが支持されるという議論がある(Hammond 1996; Hayes et al. 2018)。しかしこれは誤りである。単一過程モデルは、過程数こそ少ないが、それ以外の点で多くの理論的過程を必要とする(Gawronski & Creighton 2013, Kruglanski & Gigerenzer 2011)。倹約性はすべての理論的仮定の観点から評価されなければならないため、単に過程数が少ないという理由だけで単一過程モデルが支持されるわけではない。
5. 科学的誤情報論法
二重過程モデルに対し、次のような実践的な反論がよくなされる。過程の二重性に明確な証拠はないが、しかし二重過程モデルは単純なので人の心に入りこみやすく、科学者の思考をゆがめたり大衆に誤情報を与えてしまう、というものだ(Cokely 2009; Melnikoff & Bargh 2018; Osman 2004, 2018)。
この議論には様々な反論がありうる。第一に、過程が一つだという主張にも決定的な証拠はないのだから、誤情報を与える点では単一過程モデルも同罪である。第二に、どのような科学的主張も誤って解釈される可能性がある(Chater 2018)。単一過程モデルは、熟慮も直観も大して変わらないという推測を生み、熟慮を避ける口実に使われるかもしれない。単一過程モデルと二重過程モデルのどちらが誤解されやすいかに関する実証的データはなく、科学者は強い主張を控えるべきだ。第三に、二重過程という概念が科学の進歩を妨げるという一般的な主張はすぐに反証できる。実際、例えば推論中の葛藤検出にかんする多くの発見が、二重過程的なフレームワークの中でなされてきた。もちろん、こうした知見は単一過程モデルでも容易に説明できるので、二重過程モデルが一方的に支持されるというわけではない。しかし二重過程的フレームワークは、いわば便利なコミュニケーションツールとしての役割を果たしてきたと言えるだろう。
第2部 論争の不毛さについて
第1部では、これまで30年に及ぶ議論の中で、単一過程モデルか二重過程モデルかを決する良い証拠は提出されていないことを明確にした。では、これからはより良い実証的証拠をさらに探すべきなのだろうか。そうではなく、この論争はもう終わらせるべきだ。それには二つの理由がある。第一に、この論争が解決可能なのか疑問である。第二により重要なことに、この論争はたとえ解決したとしても、人間の思考に関する心理学的理解を深化させない。
1. この論争は非経験的である
これまで強調してきたように、定義的特徴の特定や閾値の設定、閾値の上下での過程が質的に異なることの確認、などは非常に複雑で、どのような実験をすれば問題を解決できるのか全く明らかではない。しかしより一般的に、そもそもこの論争は経験的データでは決着がつかないと論じることができる。Gawronski et al. (2014) が指摘しているように、何が「本当に」存在しているのかに関する主張は、経験的にテストできない形而上学的なものだと考える長い哲学的伝統がある(Popper 1959, Quine 1960, Whitehead 1978)。つまり、量的変化なのか質的変化なのかという議論には、〔その状況をどのような言葉で表現すべきかという〕意味論的な議論と結びついており、後者において経験的データはほとんど役に立たないのだ。
2. この論争はどうでもよい
仮に論争が決着したとしても、心理学はそこから何かを得られるのだろうか。2過程の差異が質的か量的かが分かっただけでは、それら過程の働きや相互作用についての何も予測も得られない。具体例で考えよう。この分野において重要な問題に、どうすれば人の推論を最適化できるかという問題がある。仮に、ある課題において、熟慮が最適なパフォーマンスに繋がることが分かっているとする。ここで、熟慮と直観の間には質的な差異があり、熟慮は直観とは違ってワーキングメモリに負荷をかけるものだとしよう。この時、推論を最適化するためには、ワーキングメモリを鍛える介入が有効だろう。他方で、熟慮と直観の間には量的な差異があり、熟慮は直観よりもワーキングメモリに大きく負荷をかけるとしよう。この時も、推論を最適化するためには、ワーキングメモリを鍛える介入が有効である。つまり、二過程の差異が量的か質的かという問題は、介入方法の選択には全く関係がない。この意味で、質対量の議論はどうでもよいのだ。
思考の心理学に関する他の重要問題として、例えば次のようなものがある。第一に、直観/熟慮はどのような帰結を生むか。例えば、論理的推論、道徳的決定、利他的行動、フェイクニュースへの敏感さなどのありかたは、先立つ思考が直観的か熟慮的かによって(どう)変わるのか。第二に、人はどのような場合に熟慮するのか。第三に、直観的思考と論理的思考の時間的関係はどうなっているのか。同時に遂行可能か、一方が増えればその分他方が減るのか、全く独立なのか、云々。両過程の差異が質的か量的かが分かっても、こうした問題に対する答えへは一歩も近づけないことは明らかである。
結論:先に進むとき
二重過程モデルと単一過程モデルの論争は解決されておらず、解決できるかどうかもわからないし、解決されたとしても人間の思考を支える処理メカニズムについての理論構築には役に立たない。この論争は思考についての実証的研究にとってはどうでもいいものである。研究者の時間と資源は限られているのであり、もっと重要な問題に力を傾けるべきだ。